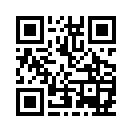母性衛生学会報告
こんにちは、代表理事の荒木です。
10/16-17まで盛岡で開催された、
第56回日本母性衛生学会に参加、演題発表をしてきました。
母性衛生学会は産婦人科医、助産師などを
始めとした、母性衛生に関わる
多職種の集まる学会で、私は初めての参加でした。
そんなわけで、女性が多いのですが、
この学会で学んだことのなかで、
特に印象に残ったことをシェアしたいと思います。
今まで、産婦人科医や助産師の方々と
連携したい、つながりたい、と
ただただ、思いばかりが強かったのですが、
この学会で、改めて再認識したことは、
「医師や助産師の方々と我々理学療法士の
立ち位置の違い」
でした。
今回の学会でもいくつか発表がありましたが、
産科の現場では、母と子の二人の命を
同時に預かり、最優先されることとなります。
まず、「生きる」ことにフォーカスがあたります。
それも、そんなに単純でも簡単でもないことです。
また、新しい命が生まれる一方で、
命が消えることも同時に起きているという、
現場でもあるわけです。
そんな感じで、グリーフケアのセッションが
あったりして、生きること、亡くなることに
ついて同時進行で捉えていかねばならない、
というのが医師や助産師に常につきまとう
ことなのではないかと、思いました。
そして、我々、理学療法士。
理学療法士はリハビリテーションの専門職。
基本的には、「回復」にフォーカスされます。
そこには、基本的に「生きる」ことが
前提になっている。
そう、そもそも立ち位置が違うから、
視点も異なるんだと気づきました。
日本の理学療法の歴史はまだまだ50年くらい。
お産は太古の昔から行われてきたことで、
やはり、理学療法はまだまだ新しいのです。
生死に対する医療には、やはり限界があります。
しかしながら、そこに全力で取り組まれる
医師や助産師、看護師の方々の尽力の結果を
維持すべく、我々はもしかしたら
力を出すことができるかもしれない、
と思いました。
そのためには、理学療法士って何なのか、
何ができて、何ができないのか。
どこまでしてよくて、どこからがいけないのか、
足元を見直すことがとても重要だと感じました。
来年は10月に東京です。
私はしばらく出向こうと思います。
大変収穫の多い学会でした^o^


10/16-17まで盛岡で開催された、
第56回日本母性衛生学会に参加、演題発表をしてきました。
母性衛生学会は産婦人科医、助産師などを
始めとした、母性衛生に関わる
多職種の集まる学会で、私は初めての参加でした。
そんなわけで、女性が多いのですが、
この学会で学んだことのなかで、
特に印象に残ったことをシェアしたいと思います。
今まで、産婦人科医や助産師の方々と
連携したい、つながりたい、と
ただただ、思いばかりが強かったのですが、
この学会で、改めて再認識したことは、
「医師や助産師の方々と我々理学療法士の
立ち位置の違い」
でした。
今回の学会でもいくつか発表がありましたが、
産科の現場では、母と子の二人の命を
同時に預かり、最優先されることとなります。
まず、「生きる」ことにフォーカスがあたります。
それも、そんなに単純でも簡単でもないことです。
また、新しい命が生まれる一方で、
命が消えることも同時に起きているという、
現場でもあるわけです。
そんな感じで、グリーフケアのセッションが
あったりして、生きること、亡くなることに
ついて同時進行で捉えていかねばならない、
というのが医師や助産師に常につきまとう
ことなのではないかと、思いました。
そして、我々、理学療法士。
理学療法士はリハビリテーションの専門職。
基本的には、「回復」にフォーカスされます。
そこには、基本的に「生きる」ことが
前提になっている。
そう、そもそも立ち位置が違うから、
視点も異なるんだと気づきました。
日本の理学療法の歴史はまだまだ50年くらい。
お産は太古の昔から行われてきたことで、
やはり、理学療法はまだまだ新しいのです。
生死に対する医療には、やはり限界があります。
しかしながら、そこに全力で取り組まれる
医師や助産師、看護師の方々の尽力の結果を
維持すべく、我々はもしかしたら
力を出すことができるかもしれない、
と思いました。
そのためには、理学療法士って何なのか、
何ができて、何ができないのか。
どこまでしてよくて、どこからがいけないのか、
足元を見直すことがとても重要だと感じました。
来年は10月に東京です。
私はしばらく出向こうと思います。
大変収穫の多い学会でした^o^